明治期、ドイツ医学導入時の医学用語の名残というのが結論。つまりドイツ語由来。
処方箋を英語でプリスクリプションというが日本では処方箋は「処方箋」としか言わない。医療事務で医療機関がお役所に対して提出する「診療報酬明細書」をわざわざ「レセプト」といいかえて内輪のことばとして使う。レセプトはドイツ語のRezeptに由来するのだが、ドイツ語のRezeptは本来「料理のレシピ」と「処方箋」の2つを意味する。「処方箋」と「料理のレシピ」の組み合わせは医食同源という言葉を連想させる。
日本語でのレセプト「診療報酬明細書」がドイツ語由来であることはわかったが、ドイツでは処方箋を表す一方、日本ではレセプトが処方箋を意味せず、診療報酬明細書だけを意味する。不思議だ。レジでもらう「レシート」領収書も、語源はラテン語のreceptusでRezeptと同源だが、日本語のレセプトはそれに近い印象を持っていた。しかし、ドイツ語辞書をめくるとRezeptに「領収書」の意味は書いていない。
推測だが、患者との間に交わす言葉で処方箋をドイツ語で「レセプト」などと高飛車にいおうものなら洒落臭え鼻持ちならん、になるだろうから「処方箋」という言葉にわかりやすくした。専門性の高い診療報酬明細書を日本では短く「レセプト」と言うが、それはおそらくジャーゴンとして使われ続けた。国立国会図書館デジタルコレクションの用語検索で戦前の文書にレセプトはなく、戦後に出てくるので制度改正時にレセプトが定義されたと思われる。現在、例えば厚生省のサイトの公式文書上でも電子レセプトと記載があり、公的文書でも認められる専門用語である。
概略、「処方箋」と「料理のレシピ」というドイツ語の本義を忘れて、現在ごく限られた意味、つまりどのような診療内容を行ったかを国に示すための文書という狭義のジャーゴンとして、「レセプト」が使われる。ドイツ語の用法にはないレシートの意味に近い気がする、なぜなら紙に明細が書いてある点が似ているから。ドイツ語からの借用語だが意味が逸れて専門用語化したと考える。
お寄りいただきありがとうございます。
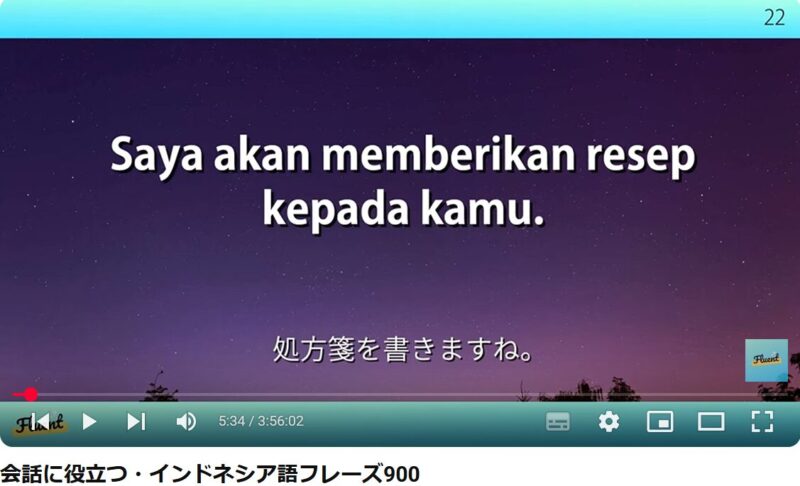
追記、余談だがオランダ植民地時代の移入語と思われるが、インドネシア語でresepが「処方箋」と「レシピ」を意味する。オランダ語を低地ドイツ語にいれる場合もある。


コメント